広告ポリシー当サイトにはPRリンクが含まれます
PRリンクの利用状況
事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(=「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
編集コンテンツの作成・運用状況
当サイトの編集コンテンツは、当社が独自に作成したものです(詳細は下記)。コンテンツ作成後にPRリンクを付与することもありますが、PRリンクによる報酬の有無がコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
- ランキング形式コンテンツ:融資時間や金利などの客観的指標をもとに順位を作成しているものであり、事業者様からの報酬の有無による順位変更は公開前・公開後問わず、一切行っておりません。
- 商品のクチコミや評価、お金の先生のQ&A:すべて当社が独自に収集した情報をもとに編集したコンテンツであり、選び方や基礎情報に関する記事は自社独自に作成した編集記事になります。
- 商品のクチコミやQ&Aの一部を掲載している場合:事業者様からの報酬の有無に関わらず社内の基準で選定を行っています。
「当サイトのおすすめ商品」の選定
当サイト内のおすすめ商品は、申込数・閲覧数などの上位から当社が選定して掲出しています。PRリンクの利用により成果報酬の対象となりますが、おすすめ商品の選定にあたり事業者様から報酬をいただくことはありません。
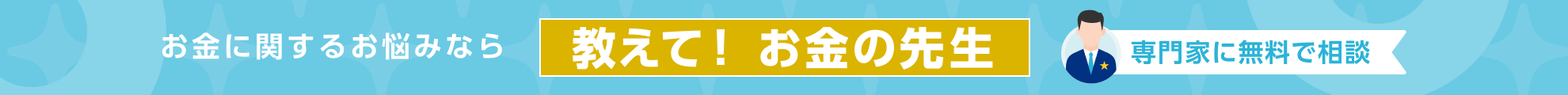
新紙幣について質問です。 7月に新紙幣になると思いますが貯蓄している口座のお金はATMで下ろせば新紙幣で出てくるのでしょうか? それとも下ろして両替するべきですか?
新紙幣について質問です。 7月に新紙幣になると思いますが貯蓄している口座のお金はATMで下ろせば新紙幣で出てくるのでしょうか? それとも下ろして両替するべきですか?あと、預金封鎖が起きた場合は貯蓄してあるお金は減ったりしますか?一時的に下ろせなくなるだけでしょうか? 無知ですみません。
回答数:1
閲覧数:117
共感した:0
ID非公開さん
質問日:2024/06/23
違反報告するベストアンサーに選ばれた回答
まず 2024年7月 と言う話を抜きにして・・・ 預金封鎖を完全否定する人間こそ詐欺師同様にお考えください 預金封鎖は 経済が混乱して起きてしまうものと 政府が意図的に個人資産を没収して 国の借金を減らすために 意図的に起こすものがあります 後者の場合は マイナンバー制度が関係してきます 1946年のようにそれまで国際的に孤立していた状態と違い 今は金融がグローバル化しており外国人資産を没収対象外にするには マイナンバーと口座紐付義務化が必須です。 そのために 免許証や保険証をマイナンバーカードと統合しようとしたりして 強制的にマイナンバーカードを持たせようとする悪い政治が行われようとしています。 預金封鎖はだまし討ちですので もし後者まで否定する人間がいるとしたら それは隠蔽工作をする側でしょうね 今自民党の裏金問題 1500万円以上をネコババして 起訴されない悪い奴がたくさんいます https://x.com/kurosuke_makuro/status/1797180795045720473 また官僚も多くの天下り先で退職金や役員報酬で税金をネコババしています こんな人間がマイナンバー利権で潤い マイナンバー制度を推進している 今の腐りきった自民党政治の中で 預金封鎖が「ありえない」と言う人は これらの人間を守って善良市民をだまし討ちしようとしている人だと思いますよ ここから本題 結論から言うと今年はないです 預金封鎖をする上で必須なのは マイナンバーと口座紐付義務化することであり それが間に合わないからです 逆に言うと これが整えば預金封鎖にまっしぐらでしょう https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13270101733 経済状態は関係ありません 預金封鎖の骨子は マイナンバーで外国人資産を没収対象外として 日本人の個人限定で 銀行のバランスシートから資産の部の国債と 負債の部の預金を相殺することです /// 1997年から大蔵省が考え始めた預金封鎖ですが、当時はマイナンバー以外にも様々な支障があります。 ①法律の不備 終戦後の預金封鎖 1946.2.17 ・勅令(大日本帝国憲法8条) ・金融緊急措置令(1963.7.22 廃止) ・日本銀行券預入令(1954.4.10 廃止) あれ? 1997年時点で法律は全部廃止されてないよね? ②日本国憲法では財産税の形にすると国会を通すのが必須になるので秘匿性が保てず法案審議中に取り付け騒ぎが起こる ③預金封鎖実行時に預金が引き出せなくなったら企業の経済活動が止まる ④日本人と外国人の資産を事前に分けないと無差別預金封鎖では国際的な批判を浴びる ところが①~③をすべて1997年以降解決させました。 ①② →預金保険法と銀行法の改正(2001年) 金融機関の生殺与奪の権限をそれまで金融再生委員会や国会が主語だったのを 内閣総理大臣に移すように改正し秘匿性が可能に、しかも「必要な措置を講ずる」と条文に入れることで「財産税」ではなく「預金切り捨て、正確には金融機関が持っている債権(国債)と債務(預金)をBSで相殺する」ことも可能になる。 ③ →新型決済性預金の創設(2002年) Yomiuri Weeklyで過去に「 ペイオフ対応新型決済性預金は預金封鎖の布石」と暴露され記事になっています ④ もちろんマイナンバーです。正確に言うと2004年に 勤労所得を除いたすべての金融資産を納税者番号制で把握する案を打ち出しています。 2004年の冒頭に当時の小泉首相が「年内に納税者番号制を実現させる」と言ったことがあります。その納税者番号制とは以下のようなものです。 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=13599 個人の年収を国が掌握することが目的じゃないです。↑で触れたとおり過去に政府税制調査会が提言している納税者番号制は 勤労所得などの捕捉ではなく 金融資産性所得限定のものです。 ちなみに 勤労所得や金融資産性所得などすべての所得を合算して課税するのを「総合課税」と言いますが、これについては大蔵省時代から現在に至るまで財務省は徹底的に反対して潰しています。そして2004年年初には小泉首相が「年内に金融資産性所得限定した納税者番号制を実現させる」と発言して その後の国会で民主党岡田克也の「勤労所得を納税者番号制に組み入れる必要はないのか?」との質問に小泉首相は「ない」と断言する答弁をしています。 このことからしても 「番号制」が正確な所得の捕捉を目的にしていないことは明らであり、金融資産を狙い撃ちにいた番号制ですね。 ④については小泉首相が「年内に納税者番号制を実現させる」と言いながら法案成立に失敗しました。もし成功していたら 2004年に成立していたことになる。 つまり 1946年に預金封鎖をした直後に日本国憲法に代わり、 50年以上預金封鎖が法律でできない状況にあったものを(しかも順次当時の法律を全滅させた) 1997年に預金封鎖の準備を始めてから たった7年間で 預金封鎖を整備を整えようとしていたわけですよ。 この時に、 2004年に 勤労所得を除いたすべての金融資産を納税者番号制で把握する案を打ち出しています。 2004年の冒頭に当時の小泉首相が「年内に納税者番号制を実現させる」と言ったことがあります。その納税者番号制とは以下のようなものです。 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=13599 個人の年収を国が掌握することが目的じゃないです。↑で触れたとおり過去に政府税制調査会が提言している納税者番号制は 勤労所得などの捕捉ではなく 金融資産性所得限定のものです。 ちなみに 勤労所得や金融資産性所得などすべての所得を合算して課税するのを「総合課税」と言いますが、これについては大蔵省時代から現在に至るまで財務省は徹底的に反対して潰しています。そして2004年年初には小泉首相が「年内に金融資産性所得限定した納税者番号制を実現させる」と発言して その後の国会で民主党岡田克也の「勤労所得を納税者番号制に組み入れる必要はないのか?」との質問に小泉首相は「ない」と断言する答弁をしています。 このことからしても 「番号制」が正確な所得の捕捉を目的にしていないことは明らであり、金融資産を狙い撃ちにいた番号制ですね。 ////// つまり 1946年の預金封鎖の根拠法は一度全て廃止さて その後は 国家破産しようと ゴジラが東京に上陸しようと 預金封鎖はできず 経済の混乱に対してもなすがままの状態を 突然1997年から 確固たる預金封鎖の意思をもって 法整備をしてきたことがわかります だから そのときの経済の混乱に関係なく 法整備ができた時点で預金封鎖に踏み切るでしょう 今は マイナンバーと口座紐付義務化ができていないので 断行することは無理です これを許すと 実行されるでしょうね
ID非公開さん
回答日:2024/06/23
違反報告する事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。
なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。