広告ポリシー当サイトにはPRリンクが含まれます
PRリンクの利用状況
事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(=「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
編集コンテンツの作成・運用状況
当サイトの編集コンテンツは、当社が独自に作成したものです(詳細は下記)。コンテンツ作成後にPRリンクを付与することもありますが、PRリンクによる報酬の有無がコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
- ランキング形式コンテンツ:取引手数料や取扱い銘柄数などの客観的指標をもとに順位を作成しているものであり、事業者様からの報酬の有無による順位変更は公開前・公開後問わず、一切行っておりません。
- 商品のクチコミや評価、お金の先生のQ&A:すべて当社が独自に収集した情報をもとに編集したコンテンツであり、選び方や基礎情報に関する記事は自社独自に作成した編集記事になります。
- 商品のクチコミやQ&Aの一部を掲載している場合:事業者様からの報酬の有無に関わらず社内の基準で選定を行っています。
「当サイトのおすすめ商品」の選定
当サイト内のおすすめ商品は、申込数・閲覧数などの上位から当社が選定して掲出しています。PRリンクの利用により成果報酬の対象となりますが、おすすめ商品の選定にあたり事業者様から報酬をいただくことはありません。
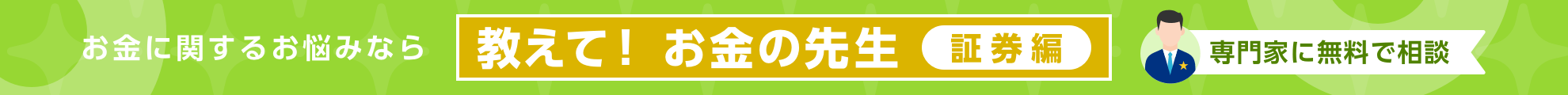
マイナンバー制度は、預金封鎖のためだと言っている人がいますが、預金封鎖は予定したり、計画してやれるものですか?
マイナンバー制度は、預金封鎖のためだと言っている人がいますが、預金封鎖は予定したり、計画してやれるものですか?
回答数:1
閲覧数:101
共感した:0
ID非公開さん
質問日:2024/05/26
違反報告するベストアンサーに選ばれた回答
預金封鎖は予定したり、計画してやれるものですか? 考え方があべこべです 予定したり 計画しないと やれませんでした。 なぜならば 1946年2月の預金封鎖の根拠法は 全て廃止されており 新しく 法律を作らないと 預金封鎖はできない状態になっていたからです。 【Q】終戦直後の新円切り替え、預金封鎖の根拠法令について知りたい。また、この法律は現在も有効か。 【A】 1 当時の根拠法令は次のものである。 「金融緊急措置令」 勅令第八十三号 昭和21年2月17日公布即日施行 資料1:p.358「預金封鎖」の項に、「昭和21年(1946)2月17日公布の金融緊急措置令および日本銀行券預入令により、3月2日を期して旧円を新円と切換え、1人百円ずつの新円と交換する以外のすべての手持ち旧円(五円券以上)を金融機関に預金させ、既存の旧円預金とともに封鎖した。」とある。 資料2:「金融緊急措置令」の項には、この措置が「昭和21年(1946)2月17日公布、即日施行の勅令」とある。 2 この法律は以下のとおりである。 昭和38年7月22日廃止 資料2:「金融緊急措置令」の項に「昭和38年7月22日廃止」とある。 念のため、官報情報検索データベースでも確認すると、 昭和38年7月22日法律第百五十九号「金融緊急措置令を廃止する法律」で廃止されていることがわかる。 また「日本銀行券預入令」も昭和29年4月10日で廃止。 つまり・・・ 昭和40年代に入れば 日本国債がデフォルトに陥ろうが どうなろうが 市場の混乱になすがままにされるだけで 預金封鎖はできなかったわけです。 それが 平成9年に 預金封鎖をするための 検討が始まり (これは 平成14年に文藝春秋や週関東東洋経済で暴露されております) 事実・・それを証明するように 平成14年~平成16年にかけて 預金保険法、銀行法、外為法などを 預金封鎖をするために都合が良いように 次々と改正されていきました (具体的には内閣総理大臣の権力強化により 国会手続きを踏まないと言う内容がほどんどであり 秘匿性を保つにはこれほど都合の良いものはない) これは 計画性以外のなにものでもありませんよ 残るは 番号制です。 昭和21年の預金封鎖との決定的な違いは 終戦直後はそれまで 国際的に孤立しており 外国人口座がほとんどなく GHQと吉田茂が 没収対象外とする資産を大蔵官僚に指令して(預金封鎖をした当時は幣原喜重郎内閣でしたが預金封鎖後すぐ辞任して吉田茂に代わった)手作業で間に合っていたのが、平成以後は預金口座が億を超え 外国人口座も多数ある状態では 手作業では間に合わないこと だから 番号で全ての金融機関口座紐付け義務化が必要 と言う話になり この案は、 預金封鎖をするための 検討が始まった 平成10年に出ています。 まず 背景を言うと 平成10年当時は 犯罪収益移転防止法の前身である 本人確認法すら成立しておらず 口座の名寄せが不十分だった。 そして証券税制は、特定口座が存在せず個人投資家の納税を代行する源泉分離課税(個人投資家の9割がこちらを選択)と自分で確定申告しなければならない申告分離課税(個人投資家の1割程度)が並立していた。 ここで 平成10年に 源泉分離課税を廃止して 申告分離課税一本化の案が出ます。 ちょっと考えるとメチャクチャですね。 ・口座の名寄せは不十分です。 ・申告分離課税の税率は高税率で大増税です。 ・確定申告を個人投資家に強要して 税務署員と投資家の事務負担を増やします。 ・源泉分離課税がなくなるということは世帯主以外の家族が株で利益をあげると 扶養控除 配偶者控除などがなくなり無関係の世帯主の所得税が増税になる可能性が出てきて、同じ金融資産でも預貯金の利子所得は源泉分離課税存続ですので 預金者に比べて完全に差別化投資家は虐待に等しい状態です。 要するに 個人投資家と税務署員の双方に負担を強い、恣意的な脱税をしやすくして、さらに 株と預金で金融資産間の不公平税制を助長する。 こんな クズ税制の計画をぶちまけておいて 同時に 「解消策」として その翌年に株も預金も含めた総合課税と納税者番号制の計画の案を打ち出すわけです。 この案を 平成10年から 16年まで毎年「実現する」と言っていたのが自民党と財務省(旧大蔵省) この案は 個人投資家や証券業協会の猛反発でお流れになりましたが 小中学生でも理解できるような制度改悪しておいて 上から目線で「解決してやるから感謝しろ」と番号制導入 口座紐付け義務化 を計画するのだから どう考えても 預金封鎖を見据えた計画性のあるものであると言えるでしょう。 平成10~16年あたりに騒がれた 証券税制と 申告分離課税一本化と 金融資産制所得限定の納税者番号制のセットにした話は お流れになりましたが その後も 何度も似たような話は出てきており マイナンバーになってからも 全ての口座紐付義務化に対する執念は 当時の流れを受け継いだものと断言できるでしょう。 この一連の流れを理解していれば 「日本が過去に預金封鎖した時は、 ハイパーインフレを終わらせると言う目的があり、 預金封鎖が行われました。 今は預金封鎖をする目的がありません。」 というのは完全に誤りであるのはわかります。 ちなみに 知恵袋では ・預金封鎖を必死に否定する人と (=預金封鎖は国民だまし討ちなので、預金引き出し、資産防衛を邪魔しようとする) ・増税に賛成してる人と ・官僚利権を擁護する人と かぶっていることが多いです。 (ID非公開で消費税増税反対の質問をすると釣れるからわかるよ) 財政が安泰だと思っているなら 消費税増税に賛成しないでしょう。 その本心は 利権関係者を守ることが 国家財政にダメージを与えていることを自覚しながら、改革無く 国民から搾り取ることを 賛成してる人ってことですよ ここまで説明しても なお 預金封鎖を ハイパーインフレ対策限定のようにミスリードしたり 脱税防止目的などとミスリードする輩がいるとすれば これまで 特殊法人や独立行政法人など 天下り先をたくさん作り 税金を貪って 国の借金を増やしてきた 権力者に尻尾を振って善良な国民を裏切り 奈落の底に突き落とそうとする 「奸物」としか言いようがないでしょう。 そうやって 人をだまし続けてきた人は 将来本当に マイナンバーと全ての金融機関口座紐付け義務化が断行され 預金封鎖になったときに 「あのときはよくもだましてくれたな」 と 非難され 鉞を持った人によって 首のところが平らになっても 「天誅だから仕方が無い」と同情されないでしょうね・・ ああ ちなみに 預金封鎖をしても憲法違反判決が出るなどあり得ませんよ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13284020878
ID非公開さん
回答日:2024/05/26
違反報告するYahoo!ファイナンスで証券会社を探そう!
初めての口座開設なら
証券会社口座開設数ランキング150社以上の証券会社から比較
証券会社比較ランキング
取引開始までの流れ
- 証券会社を選ぶ

- それぞれ特徴があるので、投資方針に合った会社を選びましょう。
- 口座開設の手続き
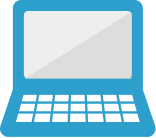
- 最近はネットで申し込めるところがほとんどです。
- 必要書類の提出

本人確認書類を提出します。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 保険証など
- 本人確認

- 自宅に送付される書類の受け取りが必要な証券会社も。スマホの操作だけで本人確認を完了できる、便利な会社もでてきています。
- 口座開設完了

- 口座に入金したら取引ができるようになります。
