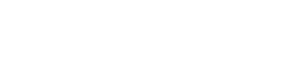初心者にもおすすめな株式の基礎をチェック!
株式は投資の主要商品のひとつ。難しそうというイメージを持つ人も多くいますが、株式自体は私たちの身近な存在で、仕組みもシンプルです。株式について知っておけば、そのほかの商品知識も身につけやすくなります。以下で詳しく解説するので、これから投資を始める人はチェックしておきましょう。
株式投資とは? ~株式のイロハ~

出典元:Getty Images
株式投資は、資金が必要な企業が発行した株式を投資家が売買する取引です。
私たちの身の回りにはたくさんの商品やサービスがあふれていますが、それぞれの企業はより良いものを提供するために試行錯誤しています。商品の開発や新しい機械の導入、人員の確保などにともない、膨大な資金が必要となるでしょう。企業は資金を集めるために株式を発行し、投資家から資金を集めます。
よく聞く株式会社とは、株式の発行によって集めた資金で経営活動を行う企業のことです。株式を購入して企業に出資する人は株主と呼ばれ、投資をした証明書として株式が付与されます。
発行される株式の数は企業が追加で発行しない限り増えないため、ある企業の株式を購入したくても、その企業の株式を保有している投資家が売らなければ取引は成立しません。人気のある銘柄の場合は、買いたい人の数に対して売りたい人の数が追いつかず、希少価値が高くなることで株価が上昇します。反対に売りたい人のほうが多い場合は株価が下がると覚えておきましょう。
どれくらいの金額から買えるの?

出典元:Getty Images
株式をどれくらいの金額から買えるのかは、株価によって変わります。株価とは、企業が発行する株式の1株あたりの価格のこと。株式の売買単位は100株に統一されており、株価に100を掛けるとおおよその購入金額を計算できます。
例えば1株1,000円の銘柄を購入する場合、1,000円×100株=100,000円に手数料を加えた金額が最低限必要です。1株が100円であれば、100円×100株=10,000円と手数料がコストとして発生します。1株がいくらかによって必要な金額が変わると覚えておきましょう。なお、売買に必要な手数料は証券会社によって異なり、なかには手数料無料の証券会社もありますよ。
通常は100株単位でしか購入できませんが、ネット証券を中心に単元未満株の売買も取引されています。単元未満株であれば1株から購入できるため、資金に不安がある人は選択肢のひとつとして検討してみてください。
株式投資の魅力

出典元:Getty Images
株式投資の主な魅力は、株価の値上がりや配当金、株主優待の3つです。
株式投資では、買ったときよりも売ったときの株価が高くなると利益(キャピタルゲイン)が得られます。企業の成長を期待して株式を購入し、株価が上昇した際に売却して利益を得ることは株式投資の醍醐味といえるでしょう。利益を得るには企業の成長予測を立てる必要があるので、経済情勢や市場分析、チャート分析などの知識が求められます。
配当金(インカムゲイン)とは、主に企業の利益の一部を株主へ還元するために支払われるお金です。金額や支払われる回数は企業によって異なり、なかには配当金を出さない企業もあります。配当金をたくさん受取りたい人は、高配当銘柄に注目して投資先を探してみるのがおすすめです。
株主優待とは、企業が株主に対して自社製品や割引券などを還元すること。持株数に応じて還元されるもので、株主優待目的で株式を購入する投資家も多くいます。株主優待の内容や回数などは企業によって異なるほか、毎年同じ内容とは限らないため、随時チェックして気になる企業をピックアップしておくといいでしょう。
株式投資のリスク・注意点

出典元:Getty Images
株式投資のリスクとして、購入時よりも株価が下落するリスクや、投資した企業が破綻するリスクがあることを覚えておきましょう。
株価は企業の業績などで下落することがあり、買ったときよりも安い株価で売却すると損失が出てしまいます。売却しない限りは購入時の株価まで戻る可能性もありますが、あまりに大きく下がりすぎると損失額が膨らむことも。株価の回復が見込めない場合は損失を食い止めることを優先し、ある程度の株価で見切りをつける選択肢も持ち合わせておきましょう。
経営状況などによって投資先が破綻する可能性もゼロではありません。場合によっては株式の価値がなくなり、投資した資金を回収できないことも。株式投資をする際は企業の経営状況や経済のニュースなどに注目し、慎重に銘柄を選ぶことが重要といえます。
リスクを回避するために有効とされるのが、業種が異なる複数の企業に分散して投資する方法です。投資先を分散させることで、ひとつの企業の株価が大きく下がっても残りの投資先で損失をカバーできる可能性があります。例えば100万円を投資する場合、1社のみに全額を投じるのではなく、30万円・30万円・40万円のように複数の企業へ分散して投資しましょう。
投資先を分散させる方法以外に、時間の分散も効果的とされています。例えば100万円を一気に投資するのではなく、時期をずらして30万円・30万円・40万円と投資するイメージです。投資タイミングを分けることで株式の買付単価が平均化され、株価の値動きに対応しやすくなります。
株価の動きをチェック(初心者向け)
株式投資の概要が理解できたら、実際に株価の動きをチェックしてみましょう。
株価はどうやって見たらよい?

出典元:Getty Images
株価はインターネットやテレビ、新聞の株価欄などで確認できます。企業ごとに割り振られている証券コードや「企業名+株価」などで検索すると、現在の株価がわかるでしょう。証券取引所や証券会社のホームページでも確認できるので、気になる企業の株価を調べてみてください。
株価にまつわる用語も理解しておきましょう。日本の株式市場は9時~15時まで取引ができ、株式市場が動き出して最初についた株価を始値(はじめね)、15時までの間で最後についた株価を終値(おわりね)といいます。
1日のなかで最も高い株価が高値(たかね)、最も低い株価が安値(やすね)です。出来高という言葉もよく耳にしますが、これは1日で取引された売買の数量(株数)を指します。
新聞やニュースでよく聞く株価指数って?

出典元:Getty Images
株価指数とは、株式市場全体や特定の銘柄群の値動きを数値化した指標です。複数の企業の株価を一定の計算式に当てはめて数値化したもので、相場を把握するためのものさしとして用いられます。日本では日経平均株価(日経225)やTOPIX(東京株価指数)などが代表的です。
日経平均株価は東京証券取引所に上場している企業のなかから流動性の高い225銘柄を選んでおり、業種などがバランスよく含まれるよう考慮されています。TOPIXは、東京証券取引所に上場する2,000以上の企業を原則すべて対象とするもの。日経平均株価よりも相場全体の動きが反映されやすいのが特徴です。
海外にも株価指数は存在し、主要なものとして米国のNYダウやS&P500、ナスダック総合指数などが挙げられます。それぞれ含まれる銘柄が異なるため、値動きの特徴を捉えて参考にするといいでしょう。
金利や為替と株価の関係

出典元:Getty Images
株価は企業業績などの内的要因のほかに、金利や為替といった外的要因の影響を受けて変動します。
金利と株価は反比例の関係にあり、金利が上昇すると株価は下落、金利が低下すると株価は上昇するのが一般的です。金利は企業がお金を借入れる際にかかるコストなので、金利が上昇すると負担がかさんで事業の拡大が滞りやすくなります。売上や利益が減ることで業績の低迷につながり、株価にも悪い影響を与えるでしょう。
反対に金利が低下すると資金を調達しやすくなるため、設備投資などに資金を投じることが可能です。事業の拡大が促進されることで売上や利益がアップしやすくなり、株価の上昇にもつながると考えられます。
為替の動きによって株価が影響を受けるのは、輸出入を行う企業です。輸出企業の場合、為替が円安になると企業の業績が上がり、株価も上昇する傾向があります。輸出品が海外で売れるとドルを円に替えて収益を得ますが、1ドル100円よりも1ドル150円のほうが収益が大きくなるからです。反対に円高のときは儲けが少なくなるため、業績の悪化と株価の下落につながりやすくなります。
一方で、輸入企業は円高のときに有利になりやすく、円安のときに業績を落としやすいのが特徴です。海外から品物を輸入する場合、1ドル150円よりも1ドル100円のほうが安く購入できるでしょう。円安のときは反対の現象が起こるため、輸入企業は円安のときに株価が下落しやすく、円高のときに株価が上昇する傾向があります。
投資初心者におすすめの資産運用3選
以下では、知識や経験が少なくても始めやすい3つの方法をピックアップしているので、ぜひ参考にしてみてください。
1.投資信託

出典元:Getty Images
投資信託とは、投資家から集めた資金をもとに、投資の専門家が株式や債権などを運用する金融商品です。投資家は出資額に応じて、運用益の一部を受取れます。
投資信託は、プロに運用を任せられるため、初心者でも始めやすいのがメリット。金融機関によっては100円からでも投資ができるため、少額から始められるのも魅力のひとつといえます。
投資信託は1銘柄に複数の投資先が組み込まれているため、分散投資も可能です。分散投資とは、複数の投資先に資金を分散させる投資方法のこと。いずれか1つの価格が下がったとしても、ほかの投資先が値上がりしていれば損失をカバーできます。
ただし、投資信託では元本が保証されない点に注意しておきましょう。運用がうまくいかなかったときは、損をする可能性もあります。
2.不動産クラウドファンディング

出典元:Getty Images
不動産クラウドファンディングとは、1つの不動産に複数人で投資する方法を指します。インターネット上で不特定多数の人から資金を調達する、クラウドファンディングサービスを使うことで、本来まとまった資金が必要な不動産投資を少額から始められます。
不動産クラウドファンディングは、物件の購入や運用を事業者に任せられるのがメリット。不動産の運用益は、投資した金額に応じて分配されます。損失が出た場合、まずは事業者の出資分でカバーするため、元本割れのリスクが抑えられていることも覚えておきましょう。
3.個人向け国債

出典元:Getty Images
個人向け国債とは、国が発行する債券を購入する投資方法のこと。適用金利が購入時に決められているほか、元本も保証されているため、低リスクで運用できるのが大きな特徴です。1万円から購入できるので、少額から投資を始めてみたい人にもおすすめ。
個人向け国債には、半年ごとに適用金利が変動する変動金利と、満期まで金利が固定される固定金利があります。変動金利の場合は満期10年、固定金利の場合は満期3年と5年から選択できるので、自分の運用方針に適したものを選びましょう。
お取引の流れ(初心者向け)
投資商品の取引方法は商品ごとに異なりますが、基本的な流れはだいたい同じです。以下で詳しく解説します。
どうやって注文したらよい?

出典元:Getty Images
投資商品は、証券会社や銀行などの金融機関を通じて購入が可能です。窓口や電話から注文を出せますが、インターネットから注文を出す人も多くいます。インターネットでは金融機関の営業員を通さず自分で発注作業を行うので、その分手数料を抑えられるケースが多いです。
例として、株式の注文方法を見てみましょう。まずは、どれくらいの株価で購入したいのか、何株ほしいのかなどを検討して銘柄を選びます。株数や売買価格、売り・買い、注文の有効期限などを指定すれば注文は完了です。
株数は配当金の金額や株主優待の内容にも影響するので、これらを重視する人は事前によく調べておきましょう。売買価格を指定する際は、価格を指定せずすぐに購入したいなら成行(なりゆき)、株価が一定の値まで下がったときに購入したいなら指値(さしね)を選択してください。
インターネットから注文を出す場合は、取引が成立したかどうかをよく確認しましょう。確認画面で終わらせてしまっていて、購入できていないこともあります。また、指値注文の場合は注文を出し続けられる期間にも注意が必要です。期間が終了して約定できていなければ、再度注文を出しなおす必要があるので気をつけてください。
手数料や税金はどれくらいかかる?

出典元:Getty Images
売買にかかる手数料は、取引する商品や金融機関ごとに異なります。インターネットからの注文は比較的安く抑えられることが多く、なかには株取引の手数料が無料の金融機関もありますよ。一定金額までは無料、それ以上は手数料が発生するような金融機関もあるので、事前によく確認しておきましょう。
投資で利益を得た場合は税金が課されます。内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%で合計20.315%です。株式の配当金や投資信託の分配金にも税金はかかるので覚えておきましょう。
ただし、NISA口座やiDeCo口座で運用した場合は運用益の全額が非課税です。加えて、iDeCoなら受取時にも税制優遇が受けられるほか、所得税や住民税の負担を軽減する効果も期待できます。投資による税金の負担を抑えたいのであれば、NISAやiDeCoを活用するのがおすすめです。
初心者が利用したい投資の制度やサービス4選
次に、投資初心者が知っておきたい、おすすめの制度やサービスを解説します。投資を始める前に、ぜひチェックしてみてください。
1.NISAのつみたて投資枠

出典元:Getty Images
NISAは日本在住の18歳以上なら利用でき、つみたて投資枠は年間120万円までの投資で得られた利益が非課税になります。投資対象は、長期・積立・分散投資に適した投資信託に限定されているので、初心者にもおすすめ。
もうひとつの成長投資枠は、非課税投資枠が240万円です。投資対象は投資信託に限らず、株式など幅広く設定されているので、つみたて投資枠に比べると本格的な投資ができます。双方は併用できるので、ニーズに合わせて柔軟な運用が目指せるでしょう。
2.iDeCo

出典元:Getty Images
iDeCoとは、個人型確定拠出年金と呼ばれる、任意で加入できる私的年金制度のことです。iDeCoは自分が拠出した掛金を自分で運用し、掛金と運用益の合計額が老後に給付されます。
iDeCoは税制上のメリットが大きく、掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の軽減が可能です。運用益も非課税になるうえ、受給時にも節税のメリットがあります。
ただし、原則60歳になるまで、資産を引き出せない点には注意しましょう。iDeCoは長期的な資産運用に適しているので、老後の資産形成を始めたい人におすすめです。
3.ポイント投資

出典元:Getty Images
ポイント投資とは、保有しているポイントを金融商品と交換できるサービスのこと。現金を使わずに投資ができるほか、少額投資も可能なことが多いため、お試しで投資を始めてみたい人におすすめです。
ポイント投資には、リターンを現金で受取れるタイプと、ポイントが増えるだけのタイプがあるので、事前にサービスの詳細を確認してから始めましょう。ポイントをためるために無駄遣いをしてしまうケースも珍しくないため、注意が大切です。
4.ロボアドバイザー

出典元:Getty Images
ロボアドバイザーとは、投資家の代わりにAIが自動で資産運用やアドバイスなどを行ってくれるサービスです。ロボアドバイザーでは、投資家のリスク許容量に配慮した投資方法の提案や、資産配分の調整なども任せられます。情報収集の時間をかけることなく投資ができるので、普段忙しい人にもぴったりです。
ロボアドバイザーは長期的な投資を目的に資産運用をする傾向にあるため、短期間での利益を期待するのは難しい点を理解しておきましょう。場合によっては、元本割れすることもあります。
ロボアドバイザーには、最適な資産運用の配分などを提案するアドバイス型と、投資商品の買付や運用なども一任できる投資一任型があるので、自分に合ったロボアドバイザーを選ぶことが重要です。
投資初心者が資産運用で失敗しないための心構え
投資を始めてみたいものの、リスクに不安がある人も多いのではないでしょうか。ここからは、投資初心者が資産運用で失敗しないための心構えを解説します。
まずは少額投資から始める

出典元:Getty Images
投資初心者は、まず少額投資から始めてみると良いでしょう。金融機関によっては100円から投資ができる商品も用意されているため、投資に慣れていない初心者でも気軽に投資を始められます。
資産運用では多くの場合で元本割れのリスクがあるため、余裕資金で投資することも大切です。少額投資であれば損失のリスクも抑えられますが、得られる利益も少なくなりやすいことは理解しておきましょう。
長期の積立投資を心がける

出典元:Getty Images
投資初心者は、長期の積立投資を心がけましょう。長期運用であれば、複利効果が期待できます。複利効果とは、運用で得た収益を再投資することで、雪だるま式に利益が増えていくこと。運用期間が長くなるほど、複利効果は大きくなります。短期間での投資は利益が安定しづらく、ハイリスクな投資になりがちなので注意しましょう。
定期的に一定額を積み立てる積立投資であれば、高いときには少なめに、安いときには多めに購入できるので、金融商品の平均購入単価を下げることも可能です。一度に購入してしまうと短期的な価格変動の影響を受け、大きな資産の減少につながるケースもあります。
分散投資でリスクを抑える

出典元:Getty Images
投資のリスクを抑えるためには、分散投資が重要です。分散投資とは、価格変動のリスクを抑えるために、複数の商品に投資をすること。
例えば、1つの商品に集中投資した場合、その商品の値動き次第で資産の価値が大きく変動してしまいます。分散投資であればいずれかの価値が下がっても、ほかの投資先でカバーできるのがポイントです。
分散投資を行う際は、投資対象の地域を分散させることや、購入するタイミングを分散させることも心がけましょう。1つの商品に複数の投資先が組み込まれた投資信託や、金融機関に資産を預けて管理や運用を任せられるファンドラップを活用すれば、初心者でも手間なく分散投資ができます。
投資の目的や目標額を決めておく

出典元:Getty Images
投資を始める際は、目的や目標額を決めておきましょう。資産運用にはリスクがともなうため、投資をする際は慎重な判断が必要です。ライフプランに合わせた目的や目標額、目標期間をあらかじめ設定しておくことで、リスク許容度や運用方針を決めやすくなります。
例えば、短期間で大きな目標額を設定する場合であれば、ハイリスクハイリターンな運用方法を考えなければなりません。老後の資金作りなど長期的な目標であれば、大きなリスクを抱えなくても、安定した運用方法で投資を始めることが可能です。
資産運用で起こりうるリスクを理解する

出典元:Getty Images
資産運用のリスクとは、値動きの振れ幅を指し、マイナスだけでなくプラスに振れるタイミングも含まれます。代表的なリスクが、金融商品の値動きによる価格変動リスクです。金融商品の価格はさまざまな要因により日々変動するため、期待していたリターンを得られない可能性があります。
価格変動リスクのほかにも、金利変動リスクや信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがあり、それらは価格変動リスクと結びつくことが一般的です。
一般的にリスクとリターンは比例するため、ハイリターンを求めればその分ハイリスクな投資をしなければなりません。リスクを正しく理解し、分散投資などで対策を講じることが資産運用におけるリスクとの上手な付き合い方といえるでしょう。
投資初心者に多い3つの失敗とは?
投資を始める前に、投資初心者がやってしまいがちな失敗例もチェックしておくといいでしょう。ここでは3つの失敗例を紹介します。
投資初心者の失敗①:無理な投資額を設定してしまう

出典元:Getty Images
投資初心者のよくある失敗として、無理な投資額を設定してしまうことが挙げられます。投資額が大きいほど値上がりした際の利益も多くなりやすいですが、投資商品は売却するまで金額が確定しません。急な出費が必要になったとき、利益が出た状態であるかは不透明です。
すぐに使える現金が手元にないと、本来は手放したくないタイミングで売却しなければならなくなることも。投資資金を増やしすぎて生活に困ってしまっては本末転倒です。手元にはある程度の現金を残した状態で、しばらくは使わないお金を投資に回しましょう。
投資初心者の失敗②:投資の結果に一喜一憂する

出典元:Getty Images
どれくらい値上がりしているのか、大きく減ってしまっていないのかが気になり、投資の結果を日々細かくチェックして一喜一憂するのも投資初心者によくあること。マイナスが出ていると怖くなってすぐに損切りしたり、反対に少しプラスが出たところで利益確定したりしてしまう人もいるでしょう。
投資商品にもよりますが、基本的に投資は長期目線で考えて、トータルの資産を増やしていくもの。わずかな値動きで何度も売買を繰り返すと複利効果も得られないため、目先の値上がり・値下がりに惑わされずにじっくりと向き合うことが大切です。一時的な変動に一喜一憂せず、長期で資産を増やしていきましょう。
投資初心者の失敗③:人の意見に左右される

出典元:Getty Images
投資の知識に自信がない投資初心者は、投資歴の長い人の意見に左右される傾向があります。身近な友人や金融機関の担当者、SNSなどの情報を鵜呑みにして失敗したときは、つい他人のせいにしてしまうかもしれません。
しかし、投資をする以上は損失が出ても自己責任です。周りの情報を参考にして知識を身につけるのは良いことですが、すべての情報が正しいとは限りません。情報を鵜呑みにして行動するのではなく、自分自身でも調べたり考えたりして、自分の判断で投資を行いましょう。
証券会社を比較検討するならランキングを参考に
証券会社には店舗型とネット型があり、どこで口座を開設するべきか悩んでしまいますよね。
各社の詳細を見たいときは、以下のページをチェックしましょう。各証券会社をランキング形式で紹介しており、特徴ごとに絞り込む機能もあるので、口座開設先を選ぶ際の参考にできます。