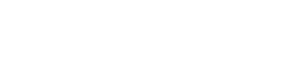大学生が理解しておきたい投資と貯蓄の違い

出典元:Getty Images
投資と貯蓄の違いは、以下のとおりです。
- 貯蓄:預貯金や現金などすぐに使えるお金
- 投資:お金を使って有価証券や債券などを購入すること
日本の普通預金の金利は0.001%程度と非常に低いため、銀行に預けていてもほとんど増えません。また、日本は2022年からインフレ傾向にあり、2024年3月の消費者物価上昇率(インフレ率)は前年同月比2.7%プラスと大きく上昇しています。物価が上昇してもその分給料が上がらないのであれば、生活費が上がって収入が増えないので生活は苦しくなるでしょう。
預貯金だけの資産運用では、物価上昇による生活費の増加に勝てません。対して、資産運用なら年間3〜5%ほどの収益を期待できます。これからは、一定割合を投資に振り分けて資産運用をするべきといえるでしょう。
※参考:総務省・2020年基準 消費者物価指数 全国 2024年(令和6年)3月分(外部サイト)
大学生が投資を始めるメリット
投資は将来の資産形成において重要な位置づけになってきています。そのなかで大学生のうちから投資を始めるメリットは3つあります。
長期間投資ができるので収益が安定しやすい

出典元:Getty Images
社会人になってから投資を始めるのと比べて、長期間投資ができるので収益を安定させることが可能です。株式や投資信託などに長期投資すると、短期投資より収益の振れ幅が小さくなります。
一般社団法人投資信託協会の資料によると、1962年〜2021年までの間でTOPIX(東証株価指数)に5年投資した場合、40年投資した場合の最低収益率〜最高収益率は以下のとおりです。
<TOPIXの投資期間ごとの収益幅>
- 5年投資:-13.8%~+32.9%
- 40年投資:+4.6%~+10.4%
あくまで過去のTOPIXのデータであるため絶対ではありませんが、投資期間が長ければ長いほど、収益は安定する傾向にあります。
※参考:一般社団法人投資信託協会・第3回 長期投資のメリットとは(外部サイト)
自分の時間を確保しながら収入を得られる

出典元:Getty Images
自分の時間を確保しながら収入が得られます。大学生がお金を稼ぐ手段としてはアルバイトが一般的です。ただし、収入を増やそうとすると勤務時間を増やさなければいけません。
投資なら、自分が働いていない時間でもお金が増える可能性があります。投資で収入が得られれば、授業やサークルなどの活動に時間をあてることができるでしょう。
金融の知識が身につく

出典元:Getty Images
投資を始めることで、金融の知識が身につきます。株式投資である程度の利益を出すためには、企業の成績(業績)や財務状況などに関心を持たなければいけません。
また、投資の知識は利益を得るためだけでなく、さまざまな場面で活かせます。企業の業績や財務状況がわかれば、よい就職先を探せる可能性も上がるでしょう。専門的な会計の知識をつければ、就職に有利になる可能性もあります。
プロにお任せできる投資信託でも、国の政策や海外の経済政策などに関心を持たなければいけません。金融の知識は、就活にプラスに働くだけでなく、詐欺的な投資に騙されないためにも必要です。
投資を始めるならまずは少額投資からがおすすめ

出典元:Getty Images
大学生が投資をするなら、数百円から10万円程度の少額投資から始めてみるのがおすすめです。
少額投資のメリットは、余剰金が少ない状態でもまとまったお金を用意せずに始められること。株式投資をする場合は初期投資として10万円以上を用意しなければいけないケースも多いですが、少額投資なら数百円程度から気軽に投資できます。
ひとつの商品にかかる資金が少額で済むことから、さまざまな商品を購入しやすい点もメリットです。複数の商品に投資して投資先を分散させれば、価格変動のリスクもカバーしやすくなります。また、投資では損失を出すリスクがつきものですが、投資資金が少なければ損失額も小さくなりやすいため、大きなダメージになりにくいでしょう。
少額とはいえ実際に取引をするため、実践的な練習ができるというメリットもあります。投資をするうえでは想定外の事態に直面するケースもあり、その都度自分自身で判断しなければいけません。少額投資なら失敗しても損失を抑えやすいため、積極的にさまざまな手法を取り入れられるでしょう。
大学生が理解しておきたい投資のリスクや注意点
大学生のときから投資を始めるメリットは大きいですが、一方で注意すべき点もあります。ここでは投資のリスクや注意点を5つ紹介するので事前にしっかりチェックしておきましょう。
詐欺に引っかからないようにする

出典元:Getty Images
投資を始める際は、詐欺に引っかからないようにしましょう。原則として、金融庁から登録を受けた金融商品取引業者や暗号資産交換業者以外からは購入してはいけません。
実際に、金融庁から登録を受けていない企業や個人から未公開株や新規公開株、暗号資産などの勧誘を受けて購入した人は、詐欺的行為により資金を失うなどのトラブルが発生しています。
特に、「年利30%保証」など本来ありえないような利回りを謳う商品には十分注意してください。正しい金融知識を身につけて、騙されないようにしましょう。
生活を圧迫するほどに資金を投下しない

出典元:Getty Images
生活を圧迫するほどに資金を投下しないようにしましょう。投資はお金が増えるだけでなく、損して減る可能性もあります。生活費や学費など、すぐに支払いが必要なお金に投資してはいけません。
投資は余剰資金で行うのが鉄則です。
確定申告や所得控除について知っておく

出典元:Getty Images
確定申告や所得控除など、税金に関する知識も身につけておきましょう。株式投資や投資信託なら、証券口座を作るときに「特定口座・源泉徴収あり」を選択すれば確定申告は不要です。
一方で、FXや暗号資産などに投資する場合は確定申告が必要になります。投資収入に対して発生する税率は、原則として20.315%です。FXや暗号資産は雑所得となり、税率や計算方法が異なるので注意しましょう。
アルバイトをしている人は、アルバイトの収入を含めて103万円以上の収入があると所得税が発生する可能性があります。扶養親族から外れて親の所得税が増える可能性もあるので、アルバイト収入が多い人は特に注意してください。
損失が出る可能性があることを理解しておく

出典元:Getty Images
投資は損失が出る可能性がつねにあります。たとえプロの投資家でも損することはあるので、初心者はなおさらです。確実に損しない方法はありませんが、買うタイミングや銘柄を分散することでリスクを分散できます。
毎月5,000円を同じ銘柄に投資する時間の分散や、日本や海外を含む世界中の株式に投資する投資信託を選ぶ投資地域の分散がリスク分散の一例です。
リターンを求めるほどリスクが大きくなることが多いので、初心者のうちは大きなリターンを求めすぎず、着々と利益を増やす運用がおすすめです。
ちなみに投資のリスクにはいくつか種類があります。以下で紹介するので、投資にはどのようなリスクがあるのかをおさえておきましょう。
株価の下落や急落

出典元:Getty Images
株式に投資する場合は、株価が下落するリスクがあります。株価が変動する主な要因は、企業の経営状況や景気、社会情勢など。株価が上がったり下がったりする可能性は株価変動リスクと呼ばれ、株式投資ではつねに株価変動リスクを抱えることになります。
株価が大きく上昇すればその分リターンも期待できますが、株価が下落すると損失が出たり、最悪の場合は元本割れを起こしたりする可能性も。下落や急落による損失に備えるためには、分散投資でリスクを抑える、生活に影響が出ない余剰資金で投資するなどの対策が必要といえるでしょう。
投資先企業の突然の倒産・上場廃止

出典元:Getty Images
投資先企業の突然の倒産や上場廃止により、損失を出すこともあります。企業が倒産すると、場合によっては株式の価値がなくなって元本割れを起こすことも。このようなリスクは信用リスクと呼ばれます。信用リスクを抑えるには、財政難や経営不振に陥りにくそうな投資先を選ぶことが大切です。
また、不祥事などによって上場廃止が決定した場合は、買い手が見つからず売却しにくくなります。このようなリスクは流動性リスクといい、上場廃止後は市場を通した取引ができません。上場廃止から1カ月間は整理銘柄として取引できますが、値がつかずに売却先が見つからなかったり、想定より安い価格になったりするケースもあります。
流動性リスクを避けるには、売買量が活発とされるプライム市場の銘柄や大企業の銘柄を候補に入れましょう。なお、上場廃止後も取引所を通さない売買や保有、配当金の受取りは可能です。経営戦略による上場廃止の場合、売買の仕方によっては利益を得られるケースもあるので、情報収集したうえで投資戦略を考えましょう。
学業やアルバイトなどとの両立が難しくなる可能性も

出典元:Getty Images
投資のやり方によっては、学業やアルバイトとの両立が難しくなる可能性もあります。短期投資を行う場合、常にスマホやパソコンで値動きをチェックしなければいけません。
投資に熱中しすぎると、大学の授業やアルバイトが疎かになる可能性もあります。できる限り長期投資を行うか、スキマ時間を効率的に活用しましょう。
基本的な投資の始め方もおさえておこう
大学生で投資を始めようと考えている人は、投資の始め方も簡単におさえておきましょう。投資は4ステップで始められます。
ステップ1:運用資金を用意する

出典元:Getty Images
投資するための運用資金を用意しましょう。投資は最低100円程度から始められますが、あまりに資金が少ないと利益がほとんど出ません。
少なくとも数万円は用意しておくとよいでしょう。日本株式に投資する場合は、1株から買える証券会社を利用すれば、10万円で大半の銘柄が買えます。日本株式を1株から投資したい人は、SBI証券の「S株」やマネックス証券の「ワン株」など少額で投資できる方法をチェックしてください。
また、米国株式も1株から購入できるので、比較的運用資金が少なくても株式投資を始められます。
ステップ2:金融機関を決めて口座開設する

出典元:Getty Images
運用資金が用意できたら、金融機関を決めて口座開設しましょう。実店舗のある証券会社と比べて手数料が安いSBI証券や楽天証券などのネット証券がおすすめです。マイナンバーがわかるものと本人確認書類を準備しましょう。
スムーズに口座を開設するためには、以下いずれかの書類が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証+通知カード
スマホで本人確認できれば、最短翌日で口座開設できます。
ステップ3:開設した口座に入金する

出典元:Getty Images
口座を開設したら、証券口座に入金します。入金方法は、即時入金サービスの利用や系列銀行と連携した入金サービスを利用するのが一般的です。銀行振込もできますが、振込手数料がかかる場合があります。
スムーズに入金したいなら、同グループ内に証券会社と銀行があるサービスに注目。SBI証券は住信SBIネット銀行やSBI新生銀行、楽天証券は楽天銀行と連携しているため、この2社に口座開設する場合は銀行口座も作るとクイックに送金できて便利です。
ステップ4:取引をスタートする

出典元:Getty Images
入金したら取引をして、投資を始めましょう。取引をする際は注文方法を理解するだけでなく、株式や投資信託などの金融商品に関して事前に勉強することが大切です。一度成立した注文は、取り消しができない点は覚えておきましょう。
大学生におすすめの投資の種類
大学生におすすめの投資は4種類あります。初心者は、リスクが低いものからスタートするのがおすすめです。
少額からでも始められる投資信託

出典元:Getty Images
最低100円から始められる投資信託は、投資初心者におすすめです。自分で投資先(企業)を選ぶ必要がある株式投資と異なり、投資信託なら「日本株式に分散投資したい」「米国株式に分散投資したい」などの大まかな投資方針から選べます。
投資信託は、幅広い投資家から資金を集め、まとまった資金を活用してプロが運用する商品です。投資信託には、大きく分けて2種類あります。
- インデックスファンド
- アクティブファンド
インデックスファンドは、日経平均株価やダウ平均株価などの指数に連動した投資成果を目指します。アクティブファンドは指数に上回る投資成果を目指す投資信託ですが、インデックスファンドの投資成果を必ず上回るわけではありません。
投資信託には、信託報酬をはじめとした手数料がかかります。インデックスファンドのほうが手数料が安い傾向があるので、まずはインデックスファンドから選んでみましょう。
企業の知識も学べる株式投資。単元未満株・ミニ株なら少額取引が可能

出典元:Getty Images
企業に関する知識も身につく株式投資もおすすめです。投資信託と異なり、自分で投資先(企業)を選ぶので、企業へ投資しているという実感も持ちやすいでしょう。配当金や株主優待がもらえる銘柄があるのも魅力的です。
先述のとおり、日本株式は原則として100株単位で投資する必要がありますが、証券会社によっては1株からの投資ができるところもあります。少額で株式投資ができる商品は単元未満株といい、証券会社によって「ワン株」や「S株」など呼び方が異なりますが、1株から買える点では同じです。また、10株単位から取引ができるミニ株という商品もあります。
1株なら500~1,000円程度で有名企業の株式が買えるので、まとまった資金を用意できない人も気軽に始められるでしょう。
プロが不動産投資をしてくれるREIT

出典元:Getty Images
少額から不動産に投資できるREIT(不動産投資信託)もおすすめです。REITは、投資信託と同じように投資家から資金を集めて不動産に投資します。不動産は安くても数百万円以上、金額が高い物件では億単位の資金が必要ですが、REITで価格が安い銘柄なら10万円以内です。
REITは、主に不動産の賃料を配当として投資家に分配するため、比較的安定した配当収入が期待できます。不動産と異なり株式市場で株式のように自由に取引できるので、少額から不動産に投資したい人はREITを選びましょう。
上場企業を対象にしたETF

出典元:Getty Images
ETF(上場投資信託)も選択肢のひとつです。ETFとは上場投資信託のことで、投資信託とは異なり株式のように取引所で売買できる点に特徴があります。市場で取引されている価格ですぐ取引できるため、一部の投資信託のように売却が翌営業日になってしまうことはありません。
株式投資のように投資したい個別の企業がなく、投資信託より素早く取引していきたい人は、ETFを選ぶとよいでしょう。
運用の仕組みは投資信託とほぼ同じです。日本のETFよりも米国をはじめとした海外のETFのほうが手数料(信託報酬)が安い傾向があります。
税制上のメリットを受けられる投資の制度もチェック
投資には、税制上のメリットを受けられる制度が2つあります。基本的に誰もが利用できる制度なので、投資を始める際は目的にあわせてぜひ活用しましょう。
非課税投資枠が設けられているNISAのつみたて投資枠

出典元:Getty Images
1つ目は、非課税投資枠が設けられているNISAのつみたて投資枠です。NISAのつみたて投資枠は、金融庁が少額からの長期・積立・分散投資を支援するために設けた制度で、長期投資に向いている投資信託やETF8本だけに投資できるようになっています(※2024年2月29日時点)。
NISAのつみたて投資枠については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてチェックしてください。また、NISAのつみたて投資枠を利用できる証券会社をランキング形式で紹介しているページもあるので、口座開設先を検討する際に参考にしてみましょう。
※本記事に掲載されている情報は2024年5月16日時点のものです。NISA制度に関する最新の情報は、金融庁の公式サイト(外部サイト)をご確認ください。
自分にぴったりのNISA(NISAのつみたて投資枠)開設先を探す
投資した利益は非課税になるので、投資信託で長期投資を考えている人におすすめの制度です。
老後資金を積立したい人におすすめのiDeCo

出典元:Getty Images
もうひとつは、老後資金を積立したい人におすすめのiDeCo(個人型確定拠出年金)です。iDeCoは20歳から加入できる制度で、投資信託などの商品を選んで毎月、隔月、毎年など一定額を積み立てます。会社員、公務員、自営業者によって上限額が変わり、積立金の上限額は最大月68,000円です。
iDeCoは60歳まで引き出すことができない点や一度始めると原則として途中で脱退できないデメリットがありますが、投資利益が非課税になるだけでなく所得控除も受けられます。収入があって国民年金を納めている大学生であれば、iDeCoへの加入を検討してもよいでしょう。
以下のページでは、iDeCoを取扱う金融機関について詳しい情報を掲載しています。iDeCoについて気になる人はぜひ参考にしてみてください。
大学生の投資に関するQ&A
大学生の投資について、よくあるQ&Aをまとめました。危険性や勉強方法などについて解説しています。
おすすめの勉強方法とは?

出典元:Getty Images
まずは本を読んで投資やお金について学ぶのがおすすめです。基礎からわかりやすく解説している本が多数販売されています。YouTubeやブログなどのSNSでも情報収集することが可能です。勉強会やセミナーを実施しているところもあります。
ただし、インターネットやSNSのなかには信ぴょう性に欠ける情報も含まれていることがあるため、発信している人の経歴や実績は確認しましょう。
投資以外にもお金を稼ぐ方法はある?

出典元:Getty Images
アルバイトをはじめとした労働所得、YouTubeやブログなどの事業所得があります。
労働所得は、大学生である程度講義が少ない人なら週3日、1日5~7時間程度はシフトに入れるでしょう。時給1,000円と仮定すれば月2~3万円は稼げます。
YouTubeやブログは、動画や記事を作って広告収入を得る方法です。YouTubeは一定の要件(チャンネル登録者1,000人、年間4,000時間再生)を満たしたうえで動画が1回再生されるごとに広告収入が入ります。
ブログの主な広告収入は、Googleアドセンスとアフィリエイトの2種類です。Googleアドセンスは、広告をタップまたはクリックしてもらうと広告収入が入ります。アフィリエイトは商品やサービスを紹介して、サイトを訪問した人が自分の記事を経由して商品の購入、サービスの利用につながると広告収入が入るシステムです。
大学生が投資をするのは危ない?

出典元:Getty Images
投資にはリスクがありますが、危ないわけではありません。
口座にある資金の3倍まで取引できる株式の信用取引の場合は、損失が発生した際に払いきれない金額の損失(借金)が発生する可能性はあります。ただし、ここで紹介した投資手法では、購入金額以上の損失は発生しません。
正しい知識を身につけて少額から始めれば、投資に失敗しても取り返しのつかない結果にはなりにくいでしょう。自分の所持金や投資できる金額を見極めて、少しずつ慣れていくことが大切です。
証券会社を比較検討するならランキングを参考に
証券会社の利用を検討している人は、以下のページをチェックしましょう。各証券会社をランキング形式で紹介しています。特徴ごとに絞り込む機能もあるので、比較検討する際に参考にしてください。