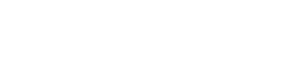社会人1年目(新卒)の貯金事情
まずは、新卒で社会人1年目の平均貯金額や理想とされる貯金額を紹介します。収支の状況は人それぞれ異なりますが、一般的な目安を理解しておくことは大切です。
社会人1年目の平均貯蓄額は49万円

出典元:Getty Images
ソニー生命の2024年の調査によると、社会人1年目の平均貯金額は49万円程度という結果が出ています。貯金額別の割合は0円が13.4%、10万円未満が17.0%、10万円以上20万円未満が11.0%、20万円以上30万円未満が8.4%、30万円以上40万円未満が4.6%、40万円以上50万円未満が2.4%、50万円以上100万円未満が19.4%、100万円以上が23.8%です。
社会人1年目で100万円以上の貯金がある人もいれば、同程度の割合で一切の貯金ができていない人もいます。収入や生活スタイルは人それぞれ異なるので、49万円はひとつの目安にしてみてください。
貯金できる金額は、一人暮らしか実家暮らしかでも大きく変わります。例えば、実家暮らしの場合、家賃や食費などの出費を節約できるので、一人暮らしよりも貯金しやすいのが一般的です。
※参考:ソニー生命保険株式会社・社会人1年目と2年目の意識調査2024(外部サイト)
新卒の理想貯金額を初任給から考えてみよう

出典元:Getty Images
1年間に49万円をためるには、月々約4万円の貯金が必要です。
厚生労働省の調査によると、新卒の平均的な初任給は、大学卒で23万7,300円。各種保険料などを差し引いた手取りは額面給料の約80%といわれており、計算すると約19万円です。4万円÷19万円=0.21となるため、貯金額49万円を目指す場合は手取りの2割程度を貯金するのが理想といえるでしょう。
平均初任給は、高校卒が18万6,800円、専門学校卒が21万4,500円、高専・短大卒が21万4,600円、大学院卒が27万6,000円と学歴によっても大きく異なります。それぞれの給料に合わせて家計を管理し、貯金することが大切です。
社会人2年目からは、住民税の徴収が始まります。住民税は前年の課税所得に基づいて計算されるため、基本的には1年目より手取りが減ってしまう点には注意しましょう。
※参考:厚生労働省・令和5年賃金構造基本統計調査(外部サイト)
社会人1年目の貯金が難しいのはなぜ?
社会人1年目は、なかなか思うように貯金ができない人もいるかもしれません。以降で、社会人1年目の貯金が難しいといわれる理由を紹介するので参考にしてみてください。
生活費にお金がかかる

出典元:Getty Images
社会人になると、学生時代よりも出費が増える傾向にあります。内訳は、通勤服の購入費用や同僚との交際費、保険料、食費、家賃、自己啓発のための書籍代やセミナー代などさまざま。一人暮らしを始めるなら、家電や家具などの購入費用も必要です。
2023年の家計調査の結果によると、34歳以下の平均的な生活費は、17万281円にのぼります。収入の多くを消費支出が占めてしまい、お金を貯金に回す余裕がない人も珍しくありません。
※参考:総務省・家計調査 / 家計収支編 単身世帯 詳細結果表(外部サイト)
社会人1年目はボーナスが少ない

出典元:Getty Images
会社にもよりますが、夏のボーナスの査定は前年度に行われるのが一般的。社会人1年目は働いている期間が短いため、夏のボーナスが少ない、もしくは、支給されないこともあります。ボーナスの有無や金額によっては、貯金が難しいかもしれません。
そもそもボーナスは、会社の業績や個人の能力などによって支給額が変動するものです。ボーナスをあてにした貯金は避けるのが無難といえます。
奨学金の返済が始まる

出典元:Getty Images
卒業後に奨学金の返済がスタートすることも、貯金が増えない原因のひとつです。例えば、日本学生支援機構の奨学金を借りていた場合、貸与終了の翌月から7カ月目に返済が始まるのが一般的。
生活費に加えて、毎月数万円の返済が上乗せされるため、社会人1年目には大きな負担になるでしょう。奨学金の返済がある人は、毎月の返済額を正確に把握しておくことが大切です。
社会人2〜3年目で貯金をするのも実は難しい

出典元:Getty Images
社会人1年目だけでなく、社会人2〜3年目も実は貯金が難しいことを把握しておきましょう。社会人2〜3年目でも貯金が難しい大きな理由は、住民税が引かれてしまうことです。
住民税とは、地域の公的なサービスの費用を分担するために、居住する市町村と都道府県に支払う税金のこと。前年の所得により支払額が決まり、社会人2年目以降は額面から住民税が天引きされる仕組みです。そのため1年目と2年目で同じ収入を稼いでも、住民税が引かれる分2年目のほうが手取りは低くなります。
多少給与が増えても住民税の金額によっては手取りが少なくなり、貯金にお金を回すのが難しいでしょう。auじぶん銀行の調査によると、社会人3年目で100万円以上の貯金がある人は45.6%であるのに対し、12.0%の人は貯金をしていないと回答しています。
社会人になってからコツコツとお金をためるためには、2年目以降も貯金が難しいことを理解しておきましょう。2年目以降に手取額が減ることも考慮したうえで、中長期的な貯金計画を立てることが大切です。
※参考:auじぶん銀行・新社会人と社会人3年目のお金(外部サイト)
社会人1年目が計画的に貯金するコツ
社会人1年目から貯金をするには、しっかり計画を立てることが大切です。続いては、貯金するためのコツを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
まずは貯金の目標額を決めよう

出典元:Getty Images
貯金を始める前に、目標額を決めておくことが大切です。具体的な目標額があれば、使えるお金と貯金に回すべきお金を逆算できます。反対に目標額が決まっていないと、毎月いくらためればいいかわからず、お金を使いすぎてしまう可能性も。
目標金額は高すぎると挫折したり、貯金がストレスになったりする可能性もあるため、現実的な金額に設定することも大切です。日常生活に支障が生じない範囲で、無理のない貯金額を設定してみてください。
家計簿をつけて支出を把握する

出典元:Getty Images
計画的に貯金をするために、家計簿をつけて収支の管理をしっかりと行いましょう。家計簿で月々の収支を把握すれば、節約できる部分や貯金に回せる金額が明確になります。支出を減らして余剰資金を確保することが、貯金を成功させるポイントです。
家計簿のつけ方は手書きやExcel、スマホアプリなどさまざま。自分が使いやすいと思うものを活用すれば、継続もしやすいでしょう。
支出の削減には固定費の見直しが効果的

出典元:Getty Images
毎月の支出を削減するためには、固定費の見直しが効果的です。固定費とは、家賃や光熱費、保険料、通信費など定期的な支払いが必要な費用のこと。固定費を見直すと、毎月の支出を削減できるので、余剰資金が増え、貯金に回せるお金を作りやすくなります。
例えば、格安スマホへの乗り換えや、契約している定額サービスの解約やプラン変更などが手軽でおすすめ。今より家賃が安い場所に引っ越せば、毎月の支出を大きく減らせる可能性もあります。
貯金用の口座で先取り貯金する

出典元:Getty Images
貯金用の口座を作っておき、先取り貯金することも検討してみましょう。先取り貯金とは、給料日がきたらすぐに決まった額を貯金用口座に移す方法のこと。給料から貯金に回すお金を先取りしておけば、使いすぎの防止につながります。貯金用と生活費用の口座を分けることで、貯金額をひと目で確認できる点もメリットです。
先取り貯金をする際は、自動積立サービスがおすすめ。貯金用の口座に毎月定額を自動引き落とししてくれるので、機械的に貯金を増やせるほか、口座を管理する手間もかかりません。
生活費の決済はクレジットカードがおすすめ

出典元:Getty Images
生活費をクレジットカードで決済すると、貯金や家計管理がしやすくなります。クレジットカードは、利用額に応じたポイント還元がある点や、会員サイトなどで簡単に利用明細をチェックできる点がメリットです。
ためたポイントで生活費を補えば、貯金に回せる現金を多めに確保できます。スマホの家計簿アプリと連携できるクレジットカードであれば、紙のレシートをとっておく必要もありません。
公共料金の支払いや、クレジットカードで現金を借入れするキャッシングなどは、ポイント付与の対象外になっている場合があります。ただし、ポイントにつられて必要以上にクレジットカードを利用しないように気をつけましょう。
副業や副収入で収入を増やすのも有効

出典元:Getty Images
貯金に回せる余剰資金を作るには、支出を削減するだけではなく、収入を増やすことも選択肢のひとつです。不特定多数の人がインターネット上で仕事を受注できるクラウドソーシングを活用すれば、すぐにでも副業を探せます。
自宅でできる副業であれば、本業が終わったあとや休日などに時間を作って取り組めるのでおすすめ。ライターや動画編集、プログラミングなど案件のジャンルもさまざまなので、自分に向いている仕事を見つけられるでしょう。
副業を始める前には、勤め先の就業規則で禁止されていないかをチェックすることが大切です。また、副業で得た金額によっては確定申告が必要になるケースもあることも覚えておきましょう。
給料がすべて手元に残るアルバイトやパートの場合は収入が20万円以下、個人事業主などの場合は経費を差し引いた所得が20万円以下だと、基本的に確定申告の必要はありません。
貯金に役立つ制度やサービスも活用しよう

出典元:Getty Images
銀行の積立定期預金や勤め先の社内預金制度など、貯金に役立つ制度を活用するのも、確実に貯金を作るために有効な手段といえます。
積立定期預金とは、普通預金から毎月決まった日に預金を積み立てる定期預金です。金融機関ごとに定められた最低入金額以上であれば、自動的に預金ができるほか、金利に応じた利子を受取れます。元本保証されているため、貯金が減ってしまう心配もありません。
社内預金制度とは、給与から天引きしたお金を従業員の代わりに企業が貯蓄する仕組みのこと。利子が付与されるほか、引き出したいときにはいつでも引き出せる点がメリットです。
社内預金制度と似た制度に財形貯蓄があります。社内預金制度では会社が預金を運用しますが、財形貯蓄では会社を通じて金融機関に預金し、運用してもらう点が大きな違いです。金利の面では、0.5%以上の金利を義務付けられている社内預金制度のほうがメリットは高いとされています。
NISAやiDeCoで積立投資をするのも選択肢のひとつ

出典元:Getty Images
NISAやiDeCoを活用した積立投資も貯金を増やす方法のひとつです。社会人2年目の人が目標とする30歳時点の貯蓄額は、平均986万円といわれています。1年目の平均貯蓄額49万円を基準にすると、986万円をためるまでに20年程度かかるので、貯蓄の一部を積立投資に回し、効率的に増やすことも視野にいれてみましょう。
積立投資では、投資信託などの金融商品を定期的に一定額で購入するため、一時的な価格変動による損失のリスクを抑えられます。少額から始められるので、投資初心者にもぴったりです。
積立投資を行う際は、NISAやiDeCoの活用がおすすめ。NISAとは、運用益が無期限で非課税になる制度のことです。長期・分散・積立に適した商品が対象のつみたて投資枠なら年間120万円まで、上場株式や投資信託などが対象の成長投資枠なら年間240万円を上限に投資ができます。
つみたて投資枠と成長投資枠を合わせた非課税保有限度額は1,800万円まで、うち成長投資枠は1,200万円までです。つみたて投資枠の場合、ラインアップされている商品は金融庁が厳選した投資信託ばかりなので、投資の知識が少なくても安心して購入できるでしょう。
iDeCoは、老後のための資産形成を目的とした私的年金制度のこと。運用益を非課税で受取れるだけではなく、掛金がすべて所得控除の対象になるため、節税効果はNISAよりも高いといえるでしょう。掛金と運用益は原則60歳以降でなければ受取れないうえ、加入期間によっては受給年齢が後ろ倒しになる点には注意が必要です。
※本記事に掲載されている情報は2024年4月14日時点のものです。NISA制度に関する最新の情報は、金融庁の公式サイト(外部サイト)をご確認ください。
※参考:ソニー生命保険株式会社・社会人1年目と2年目の意識調査2024(外部サイト)
証券会社を比較検討するならランキングを参考に
証券会社の利用を検討している人は、以下のページをチェックしましょう。各証券会社をランキング形式で紹介しています。特徴ごとに絞り込む機能もあるので、比較検討する際に参考にしてください。
自分にぴったりの証券会社を探す