広告ポリシー当サイトにはPRリンクが含まれます
PRリンクの利用状況
事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(=「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
編集コンテンツの作成・運用状況
当サイトの編集コンテンツは、当社が独自に作成したものです(詳細は下記)。コンテンツ作成後にPRリンクを付与することもありますが、PRリンクによる報酬の有無がコンテンツの内容に影響を与えることはありません。
- ランキング形式コンテンツ:融資時間や金利などの客観的指標をもとに順位を作成しているものであり、事業者様からの報酬の有無による順位変更は公開前・公開後問わず、一切行っておりません。
- 商品のクチコミや評価、お金の先生のQ&A:すべて当社が独自に収集した情報をもとに編集したコンテンツであり、選び方や基礎情報に関する記事は自社独自に作成した編集記事になります。
- 商品のクチコミやQ&Aの一部を掲載している場合:事業者様からの報酬の有無に関わらず社内の基準で選定を行っています。
「当サイトのおすすめ商品」の選定
当サイト内のおすすめ商品は、申込数・閲覧数などの上位から当社が選定して掲出しています。PRリンクの利用により成果報酬の対象となりますが、おすすめ商品の選定にあたり事業者様から報酬をいただくことはありません。
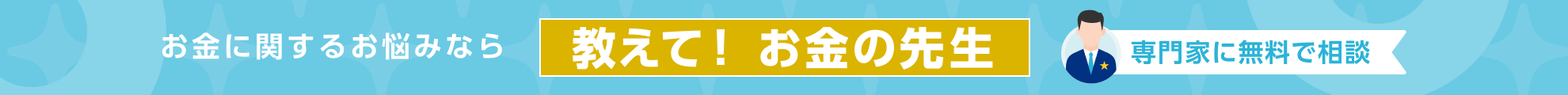
預金封鎖からの貯金税がとられるって最近よくみます。
預金封鎖からの貯金税がとられるって最近よくみます。タンス預金は新紙幣に変えられ隠せないとの事です。 新紙幣は2024年?からで新500円は2021年ですよね?例え旧新紙幣・旧500円が使えなくなるとしても、新500円をタンス預金して隠せるのでは?と思ったのですが、そんな簡単なことではないんですか? まさかゆくゆくは小銭は廃止になるとか?
回答数:3
閲覧数:1,437
共感した:1
知恵袋ユーザーさん
質問日:2020/07/08
違反報告するベストアンサーに選ばれた回答
貴方の推測されることは正しいと思います。金持ちが金地金や金貨を買うので金価格が1g=千円から、1g=6800迄上昇しているのでしょう。
回答日:2020/07/10
違反報告する質問した人からのコメント
有難うございました。
回答日:2020/07/14
その他の回答
2件
それも一つの資産防衛策としてあり得ると思います。 日本の個人金融資産は 1800兆円を超えました。 それに対して流通している 紙幣は 100兆円前後 硬貨は 4~5兆円です。 預金封鎖をする場合は マイナンバーで口座の日本人資産を確定して 主に銀行のバランスシートを 相殺することで行います。 終戦後と違うのは 終戦後はそれまで日本は諸外国と国交断絶状態で マイナンバーがなくても手作業で外国人資産を除外できたものが、今のように金融がグローバル化している状態ではマイナンバーが必須であること もう一つは、終戦後の預金封鎖は 国→軍需産業→銀行→預金者 のように 債務者と債権者の関係があったのに対して 今は軍需産業がなくなって 国→銀行→預金者 となっていること。 つまり、銀行のバランスシートから負債の部である預金と 資産の部である国債を相殺することになる。 ここからタンス預金や硬貨は没収対象から漏れますが それを新円切り替えとセットにしてやるかどうかがネックになります。 ですが、上記説明通り、流通硬貨は比率で低いので 【希望的観測を言うなら】質問者様の言う通り 硬貨が対策になるかもしれません。 ですが 円よりも他の資産防衛策も考えた方がいいでしょう。 日本政府の力で価値を落とせない 外貨や貴金属などです。 但し、これも200万円以上の売買では犯罪収益移転防止法(貴金属業者などはこの金額を超えた売買は報告義務と7年間記録保管義務があります)で捕捉される恐れがあるので、それ以下の金額で分散購入する必要があります。念には念を入れるなら 購入したものは7年以上売却しないことですね。記録が消えたら売却しても出所は国は掴めませんし もに国が預金封鎖逃れを「脱税」と決めつける暴挙に出た場合の時効対策にもなるからです。 自宅に家宅捜索はあり得ません。 国税庁の職員は6万人しかいませんので 5000万世帯を超える家にも立ち入り検査もできませんし、国税徴収法に基づく裁判所の令状発行能力も追いつきませんから。 ******* 終戦後の預金封鎖 1946.2.17 ・勅令(大日本帝国憲法8条) ・金融緊急措置令(1963.7.22 廃止) ・日本銀行券預入令(1954.4.10 廃止) 手順としては 日銀券と新券を交換し、旧券を強制預入させ、預貯金の支払いを制限する(生活するうえで必要な払い出しだけ認める) こうやって預金封鎖します。 続いて ・金融機関経理応急措置法 1946.8.15 ・金融機関再建整備法 1946.10.18 これで国家が軍需産業や金融機関に負っている債務を整理します。 最後に封鎖預金は一定額までを第一封鎖預金、それ以上を第二封鎖預金として、第一封鎖預金は今までの払い出しを制限する形で継続され、第二封鎖預金を切り捨てます。 これからマイナンバー制度で預金封鎖をする場合 現実には 終戦後の預金封鎖時の法律は全て廃止されています。ですので当時の法律に基づいて預金封鎖はできません。 ところが預金封鎖の検討が1997年より大蔵省内部で始まりマイナンバー他法整備が進んでいます。 ・預金封鎖を断行する場合は国会議事堂は一切使わず首相官邸内ですべてを処理すること(取り付け騒ぎ防止のため) ・マイナンバーのようにあらかじめ金融機関に預けてある資産を「日本人か外国人か」「個人か法人か」を事前に選別するして国際的なトラブルを避けること が主な内容です。つまりマイナンバーなどで金融資産が紐付けられるようになれば国会議事堂を通さず当然公開される形での審議もない抜き打ちの預金封鎖ができるようになります。。 大日本帝国憲法時代の財産税ならともかく 今なら 国会審議を通すので取り付け騒ぎになります だから 預金封鎖 一般人が多大な被害に遭うのは目に見えていますね その後 本人確認法や犯罪収益移転防止法が制定されましたが これも国籍を識別して国が把握できるようにはなっていません。 ですから 犯罪収益移転防止法で個々の仮名口座を撲滅できても、国は 日本人と 日本に在住する外国人を識別することができないんです。 犯罪収益移転防止法や実特法どれを調べても 国籍の情報を 銀行が国に報告することを定めている条文は存在しません。 (全国銀行協会にも確認したのでこれは間違いありません) 終戦後の国際的に孤立していた時期ならいざらず 金融がグローバル化している今の日本で現在マイナンバーなしで預金封鎖をすると 外国人資産を巻き込んで国際的に大問題になります。だからマイナンバーを使って識別するわけです。 預金封鎖は個々の脱税調査と違って 日本に存在する口座を既に国籍を識別して短期間にする必要がああります。 現時点で預金封鎖をするなら まず国籍の識別が必須。 その場合 選択肢は2つあります ・犯罪収益移転防止法や実特法を法改悪して国籍識別を徹底させ国に報告を義務付けるか、 ・マイナンバーと銀行口座を紐付けを強制するか しか二者択一しかない。しかし 既存の法律をいじる、つまり前者をするならその目的が預金封鎖と言う噂が広まる危険があるから後者しか選択肢がない。 事実 犯罪収益移転防止法や実特法を法改悪する動きはありませんが その一方で2021年から マイナンバーと銀行口座紐付けを必須にすべきとは 既に2015年の政府税制調査会の答申に出ています。 つまり 預金封鎖をするなら マイナンバー制度を使うと言う方針を立てているわけです。 このように 1997年から当時の大蔵省で預金封鎖の検討が始まりそれ以降法整備が急速に進んでいます。 ちなみに前回の新紙幣発行の時はと言うと 2004年は財務省の狙いを考えるうえで非常に重要な年です。 マイナンバーの前に財務省の意向を受けた政府税税制調査会が資産捕捉を答申したことがあります。 http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/1513.html 預金、株式、保険などの金融資産に関する損益をまとめて納税させる金融資産一体化課税というものですが、これで資産を把握して一体化課税する。そのために納税者番号制で資産を捕捉するというものです。 実現しませんでしたが実は小泉首相が2004年の冒頭に「年内に納税者番号制を成立させる」発言しました。上記のように金融資産課税一元化案も、不動産税制改悪もすべて同じ年です。さらに国会議決もなく海外送金を内閣の一存で止めることが外為法改正が行われています。 そして、この年に新紙幣発行が行われています。 新紙幣は2002年8月に「2004年4月から発行」と発表されていましたが、それが7月に延期、さらに11月まで延期になりました。 理由は「印刷が間に合わない」でしたがこんなことはありえないのです。 硬貨なら、日本國と記載された5円玉やギザギザの10円玉のように何十年も使えますが、 紙幣はすぐ劣化するので1000円札の寿命は1年と言われています。人間の細胞と同じように短期間で入れ替わるわけで、新紙幣発行当時に紙幣を70兆円か80兆円一度に用意する必要はなく逐次投入すればよいだけです。 この2002年~2005年頃は金融不安が言われており、銀行には公的資金が注入され、 さらに 足利銀行やりそな銀行のように 金融危機対応会議の結果国有化された銀行もありました。 2002年には、民主党の五十嵐文彦、古川元久、円より子 各氏の質問に塩川財務大臣が「非常に厳しい認識を持っている」「大蔵省時代から預金封鎖の勉強会を開いている」などと答弁しています。 もし、2004年あたりに納税者番号制が早期成立していたら、金融資産も不動産も全て把握してタンス預金も新紙幣発行で無効化したうえで預金封鎖を実行する と言うシナリオを抱えていてもおかしくなかったと思います。 実際のところ、納税者番号制が成立する目処が立たないので「印刷が間に合わない」などと理由にもならない理由で紙幣発行が2回延期されていた可能性も否定できないわけです。これらの経緯を考えると 将来の預金封鎖においてタンス預金が安心である保証はどこにもないと思います。 もっとも 個人金融資産1500兆円に対して現在発行されている紙幣桁違いに少ないためで財務省にとっては影響は軽微でしょうし、度重なる紙幣発行が怪しまれるなら 見逃される可能性も否定できませんが、もしマイナンバー施行後金融資産を捕捉対象にしたうえでまた新紙幣発行なんて話があるならそこが一番危ないかと思いますね
回答日:2020/07/10
違反報告するそんなまどろっこしいことしなくてもその前に 全部使っちまえばいいのに。

ID非表示さん
回答日:2020/07/08
違反報告する
事業運営のため、商品紹介時のPRリンク(「詳しく見る」ボタン)からお客様がお申込みされた場合、事業者様から成果報酬を頂いております。
なお、PRリンク自体の有無や報酬の額が、当社が編集・制作したコンテンツの内容に影響を与えることはありません。