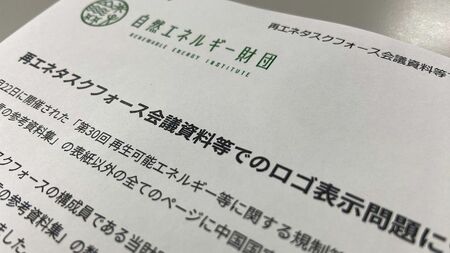ポートフォリオ
中国企業ロゴ混入で「中国のスパイ」扱いされた自然エネルギー財団の大林ミカ事務局長に聞いた
国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す「エネルギー基本計画(第7次)」の議論が始まった。経済産業省は5月15日、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長・隅修三東京海上日動火災保険相談役、委員15人)を開き、議論をスタートさせた。
現在のエネルギー基本計画(第6次)は、菅義偉前首相の「2050年カーボンニュートラル宣言」に呼応し、2030年度の電源構成に占める脱炭素電源比率を約6割と想定している。内訳は「再生可能エネルギー36~38%、原子力20~22%、水素・アンモニア1%」。
今回の見直しでは、2035年度以降の削減目標と脱炭素電源の構成比率をどこまで上げるかが注目されている。ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化などで化石燃料の地政学的リスクは高まっており、いかに純国産の再エネでエネルギー安全保障を確保するかも問われる。
ところが、である。これまでの同基本計画の改定過程で、再エネ普及の観点から専門的なシナリオを報告してきた自然エネルギー財団が、議論の輪からはずされている。理由は、内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(以下、TF)」の3月23日会合で、財団の事業局長・大林ミカ構成員が提出した資料に中国の国家電網公司のロゴが混入したことに端を発する政府の「調査」が長びいているからだ。
■事務的ミス以外の要因は浮上せず
各省庁は、調査によって財団が中国政府や中国企業の影響を受けていないことが明らかになるまでは、財団を意見聴取の対象にしないという。もちろん日本のエネルギー政策が他国の影響で捻じ曲げられるようなことは許されない。政府は検証をしなくてはなるまいが、問題発覚から2ヶ月が経ってもロゴ混入の要因は大林氏の事務的ミスのほかに浮上していない。
はたして国内で他に類のない再エネ系シンクタンクを除外して、幅広い知見を集めたエネルギー論議ができるのだろうか。
当事者である大林氏に、ロゴ混入の経緯と自然エネルギー財団が外されている背景を聞いてみた。
「そのロゴは、2016年5月に韓国で国際送電ネットワークをテーマに開催したワークショップの資料の中にありました。当時、私たちの財団以外にも、日本創成会議(増田寛也座長)や韓国電力公社、中国国家電網などさまざまな機関が国際送電網の提案をしていました。2016年の12月、諸提案を比較検討する資料を作成するため、中国国家電網の構想地図のスライドのバーを削除して日本語に翻訳する作業をおこないましたが、白地に白いロゴがなじんで見えず、削除されないまま残ってしまった。空白と表示されるスライドにロゴが入っていることに気づかず、『白地スライド』から他の資料作成を行ったため、他にも含まれてしまったのです。それが、私のプレゼンの最後の空白スライドを利用したページにロゴが入っている理由です。まったくの事務的ミスでした。タスクフォースで公表した資料の一部は私が作成したものですが、もちろんそれにはまったく国家電網の資料を使っていませんし、出典も明記しています。詳しい経緯については3月26日に『再エネタスクフォース会議資料等でのロゴ表示問題について』をリリースし、27日の記者会見でもご説明しました。総理や大臣、国会議員を含む多くの方々を混乱させましたので、私はTFの構成員を辞めました。その後、内閣府など国の省庁には4月5日付で『自然エネルギー財団へのご質問に対する報告書』を送り、その概要を8日に公表するとともに、4月16日には2回目の記者説明会を開催し、私たちが中国政府や中国の企業と人的、資金的に一切関係がないことを重ねて報告しました」
大林氏は実際にパソコンで操作をしてみせながらロゴ混入の経緯を筆者に説明した。筆者はそれで混入の原因が理解できたし、3月27日の記者会見でもマスコミの記者たちは納得していたという。事実、それ以降この問題は大手メディアではほとんど扱われなくなっている。
しかし内閣府は「調査中」を理由に、経産省や環境省は「懸念の解消」と条件づけて、自然エネルギー財団や大林氏へのエネルギー問題に関するヒアリングを止めている。
また、騒動の勃発から現在まで、ネット上や一部のメディアでは根拠もなく大林氏の国籍や名前、プロフィールまで疑うような誹謗中傷が続いている。大林氏は語る。
「ネット上で、私の名前のミカがカタカナで怪しい、中国人だ、朝鮮人だ、中国のスパイだなどと根拠なく煽っている人たちがいます。もちろん法的措置は考えています。政府の方々がデマを鵜呑みにするとは思いませんが、念のため、私と、10年前に亡くなった父の原戸籍を内閣府にはお見せしました。私の出身地は大分県の中津です。一時、私を叩いたメディアの記者さんたちも、3月27日の記者会見の後に私のところに近づいてきて、いろいろ書いてすみませんでした、社の編集方針もありまして、などと声をかけてくれました。現場の人たちはわかってくれています」
では、大林氏への攻撃や、自然エネルギー財団を排除しようとする動きは、どのように始まったのか。
■「地方公務員」を名乗ってデマ投稿
ロゴ混入の騒動は、3月22日の金曜日、第30回TFが開催された後、新電力(電力自由化によって新しく電気の小売事業を始めた企業)の関係者が翌23日10時に、資料に透かしが入っているのは何でしょうかとX(旧ツイッター)でつぶやいたあたりから始まった
その日の21時38分には「地方公務員」を自称する「Okubo@chishoin」なる人物が次のように投稿する。
「タスクフォースのメンバー4人を住基ネットで検索したことがあるんだけど、『大林ミカ』だけ該当しなかった」
この投稿をきっかけに、ネット上では「どういう人なん? 公共の仕事は出禁だろ!」「そういう人を一般的に『スパイ』と呼びますね」といった声が広がってゆく。
騒ぎが大きくなったからか、「Okubo@chishoin」はその後アカウントそのものを削除している。しかし、違法を承知で住基ネットを本当に閲覧したかのような投稿は、大林氏を中国のスパイだと信じ込みたい人たちを刺激した。デマからバッシングは盛り上がった。
過去に日本記者クラブの喫茶室で行われた共同通信のインタビューでは、偶然にも大林氏の背後に中国の朱鎔基元首相の写真が映り込んでいたことから、こちらもネット上で「大林の執務室に中国首相の写真がある」というウソが拡散した。
「実は、ロゴ問題がネット上で持ち上がったとき、私はドイツに出張中で、Xでの炎上も、ドイツ時間土曜朝に内閣府から連絡がきて知りました。土日をはさんで、25日月曜の21時ごろに帰国するまで国内では対応できませんでした。その間にデマや中傷がネット上で広がってしまったのです」と大林氏は言う。
自然エネルギー財団と中国の関係で、疑われているポイントは2つ。
まず、2016年から2019年ごろにかけて、国際的非営利組織GEIDCO(Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization)で、自然エネルギー財団と中国国家電網が交流していたことがあげられる。GEIDCOの会長に中国国家電網会長の劉振亜氏、副会長に元アメリカエネルギー庁長官のスティーブン・チュー氏とともに自然エネルギー財団設立者・会長の孫正義氏が就任した。GEIDCOとは、どんな組織なのか。
「GEIDCOは、自然エネルギー活用のための世界的な送電ネットワークの実現を目指す非営利団体です。送電網建設の世界的企業であるシーメンス、ABB、日立、GEや、世界的な金融機関グループのモルガン・スタンレー、総合コンサルティング会社アクセンチュアなども参加しており、当財団も加わりました。中国国家電網とのかかわりは、もっぱらGEIDCOを通してのものです。人的にも資金的にも当財団とは関係ありません。たとえば、今回、3人の公認会計士に財団設立以来の収入について、すべての銀行預金通帳等の関連資料を調べてもらい、中国政府・企業からのものは含まれていないことが確認されました。ロゴ混入問題が起きた後、当財団はGEIDCOを脱退しました」(大林氏)
■中国問題に警鐘を鳴らしてきた
もう一つが、GEIDCOの設立目的でもある国際間の送電網構想の立案と中国とのかかわりだ。自然エネルギー財団は2011年の設立以来、「アジア国際送電網(アジアスーパーグリッド・ASG)」構想を提唱してきた。このASGが中国国家電網を利するための構想なのではないか、という疑いだ。
「ASGは、東日本大震災後の日本の電力問題の解決策として提案したスーパーグリッド(直流高圧送電網)構築に向けた構想の一つで、ジャパンスーパーグリッド構想、東アジアスーパーグリッド構想に続く第3フェーズとして提案しました。中国国家電網とは無関係です。あくまで日本のエネルギー確保、価格低減が大前提であり、2012年の当財団のイベントでは、ASGのセッションに日本のエネルギー問題の専門家、有識者にご登壇いただいています。2019年に研究の報告書を公表し、ASGの調査を終えました。ただ、その後の国際情勢の変化で構想を進めていくのは現実的に難しくなり、いまだ構想の域は出ていません」(大林氏)
自然エネルギー財団はむしろ、中国による再エネ分野での独占や人権問題に警鐘を鳴らしてきた。
「中国は、太陽光発電設備の世界シェアの8割近く、蓄電池を構成するセルでは世界シェアの7割以上を独占しています。日本は両方とも1%前後にとどまっています。こうした中国依存は危険です。その問題性を『エネルギー安全保障の現実』というレポートで指摘してきました。中国政府のふるまいは外交面をはじめ重大な懸念を生じさせますし、ウイグルの少数民族に対する強制労働が太陽光パネルの生産にも及んでいることなどは容認しがたい、とレポートで指摘しています」(同)
一部メディアやネットの書き込みには、元経済産業省の官僚で政策シンクタンク代表を務める原英史氏も疑問を呈す。原氏は月刊『正論』6月号の「機能不全と劣化の政策決定システム」という論考の中で、自然エネルギー財団と大林氏の身に起きた騒動に触れている。
外国勢力の工作資料ではないかという声について原氏は「わざわざロゴをつけて工作活動を行う工作員がいるのか。もしいたら、よほどの間抜けだ」と一蹴。4月8日付で自然エネルギー財団が中国政府・企業との交流がごく限定的であったとする報告書を公表して以降も「影響力行使が疑われる」というのであれば、「少なくともそう主張する側は根拠を示す必要がある」と唱える。さらに、今回の騒動の背後で垣間見えるのは「河野政権の発足だけは何とか阻止したい電力業界の影だ」とも指摘する。
原氏は原発賛成派で、大林氏とは政策的な立場を異にするが、今回のような騒動で政策決定システムが劣化していくことに警鐘を鳴らした格好だ。
ロゴ混入問題について政府の調査が終結するメドは見えない。自然エネルギー財団が蚊帳の外に置かれたまま、新たなエネルギー基本計画の議論が進んでいくのだろうか。
自然エネルギー財団は、脱炭素化の方向で具体的提言をしている有力シンクタンクだ。日本のNGO(非営利組織)で、自前で電力シミュレーションをして公表できる組織はそう多くない。エネルギー基本計画の議論に、その知見は不可欠なのではないか。
東洋経済オンライン
関連ニュース
- 「親が怖くて指導できず」底辺校教師の悲痛な叫び
- 厳戒態勢で発表された「新型フェラーリ」の啓示
- 東大合格者語る「選んじゃダメな参考書」のNG要素
- 北大阪急行電鉄「箕面延伸」はこうして実現した
- 「自分は有能」と勘違いする残念な人に欠けた視点
最終更新:5/24(金) 5:21
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列
Copyright © 2024 Toyo Keizai, Inc., 記事の無断転用を禁じます。
© LY Corporation