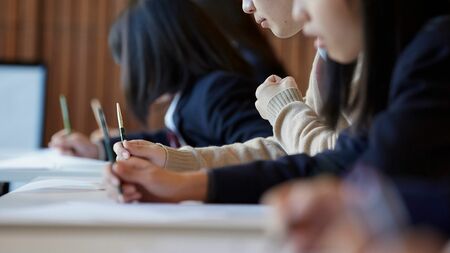【元教師が激白】「偏差値」の時代はもう終わり?“入試の新常識”とは。知らないと子どもが損をする「偏差値・入試・就活」のリアル
いい大学を出ればいい企業に就職できて将来は安泰――そのような「学歴信仰」は、今や完全に崩れ去っています。10年以上中学校教諭を務めた静岡の元教師すぎやまさんが、偏差値・入試・就活といった、気になる現場の実態を明かします。
※本稿は『教師の本音』から一部抜粋・編集したものです。
■偏差値で進学先を選ぶのはNG
子どもの「偏差値」を気にしている親御さんは多いと思います。
しかし意外かもしれませんが、小・中学校の先生が「偏差値」を念頭に置いて授業をするということは、まずありません。
なぜかというと、偏差値なんてものは、「受験産業」の中でのみ使われる概念だから。少なくとも現在の学校教育は、偏差値とはリンクしていないのです。学校教育の大元である「学習指導要領」には、偏差値なんて言葉は一言も出てきません。
それに対して学習塾というのは入試における学力テストで、いい点数をとることが目的です。それに特化しているわけですから、そりゃ学校の授業よりも効率的に点数UPを狙えるなんていうのは当然の話なのです。
それを、生徒や保護者が勘違いして、「塾のほうがわかりやすい」などと言ってくることがあります。でも、それはあくまで受験対策・点数UPテクニックとしての「わかりやすさ」。同じ教科の授業だとしても、学校の授業と塾の授業ではそもそもの目的が違うのです。
学校の授業は受験対策・偏差値対策ではありません。教育基本法や学習指導要領に基づいて、未来を担う子どもたちに必要な力をつけること。それが学校教育の目的です。
■学校と塾では方向性、指導方針がまったく違う
つまり中学校では、模試で高い点数を取ろうとか、少しでも偏差値の高い学校に生徒を押し込もうなんて、そもそも微塵も目指していないのです。
今の中学校の進路指導の基本は偏差値ではなく、生徒の将来の夢ややりたいことから逆算して、進学先を選ぶことです。
たとえば将来ゲーム関係の仕事に就きたいという子がいたら、じゃあ情報科でプログラミングを学べるこの高校がいいんじゃないか? とか、大学進学まで視野に入れているなら、理系の普通高校に行って、そこから情報工学科などがある大学に進むのがいいのではないか? という風に、生徒の思いや希望を出発点にして、進路を考えていきます。
一方、塾などの受験産業は、たとえば生徒の偏差値が56なら、偏差値55から60ぐらいの学校から興味のありそうな学校を選ぼう、という発想です。滑り止めとして偏差値55ぐらいの高校を受けておきつつ、偏差値60ぐらいのところにチャレンジできるように勉強していこう、というあくまでも「少しでも偏差値の高い学校に合格するため」のテクニックを教えていくわけです。
そもそも学校では『滑り止め』なんて言葉も絶対に使いません。「滑り止め」なんて平気で言うような人は、教育者ではなくただの点取らせ屋だと私は思います。そこを第一志望で受けている生徒や、その学校の生徒、先生方に失礼だと気づかないのでしょうか?
ただもちろん、実際に志望校に合格できるかどうか? というのは現実問題として出てきます。いくら熱心に進路指導しても、合格できなければ元も子もないので……。
だから、過去の合格実績や、成績、学力テストの結果を基にして、「ちょっとここの学校に合格するのは厳しいよ?」などと、現実的なアドバイスは、学校でも当然します。
学校と塾は、同じように授業をしたり、同じように三者面談・進路指導をしたりしているのですが、実は目指している方向性、指導方針はまったく違うのです。
■いい大学を出ても、必ずしもいい企業には就職できない
ところが塾だけでなく、保護者も「偏差値」に大きな関心を寄せています。
子どもが生まれた時には「健康で生きてさえいてくれればそれだけで十分」と思っていたはずなのに、いつの間にか「できれば勉強できてほしい、できればいい(偏差値の高い)高校や大学に行ってほしい」などと考えるようになっているのです。
偏差値の高い普通高校から、なるべくいい大学に進めば、大企業に就職できる。そうしたら将来安泰、という考えです。
でも、その考えはもう古いです。
大企業に就職するかどうかはさておき、まず、いい大学=偏差値の高い有名大学に行っておけば、進路の可能性が広がるのか? という話です。
実は現在、高卒の求人倍率のほうが、大卒よりも高くなっているのです。
高卒の求人倍率は3.52倍と、過去最高を記録(厚生労働省「令和5年度『高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況』取りまとめ(7月末現在)」)。
それに対して、大卒・大学院卒の求人倍率は1.75倍(リクルートワークス研究所「第41回ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」)。なんと高卒の約半分以下なのです。
高校生1人に対して3社以上が「うちに来てくれ」と言っているのに、大学生にはその半分ぐらいしか声がかからないことになります。つまり、今は有名大卒よりも高卒のほうが、就職先がたくさんあるという状況なんですね。
しかし、こういう話をすると、「求人倍率が高いといっても、企業のランクはどうなのかしら?」などと考える人もいるでしょう。ところが、実は最近では(特に大企業ほど)採用面接の際に「出身大学」を問わないところが増えています。中には履歴書に、大学名を書く欄がない企業もあるくらいです。
つまり、我々昭和世代がかたくなに信じてきた「いい大学に行って、いい企業に就職して将来安泰」という学歴信仰は、今や完全に崩れ去ってしまっているわけです。
■『一般選抜』は大学入試の王道ではなくなっている
そして、最近、大学受験そのものにも大変革が起こりました。2021年度入試から「総合型選抜」が始まったのです。
総合型選抜は、学力テストの結果だけでなく、その子の特技や将来の夢、活動実績なども加味して、生徒を総合的に評価して選抜しようという制度です(昔はAO入試と呼ばれていたもの)。
大学受験が暗記競争に偏ってしまった結果、問題解決能力の低い学生や、社会で生き抜く力が弱い学生が増えてしまっているという危機感を持った有名大学が旗振り役となって新設されました。
だから、この制度では偏差値がどうこうは関係ありません。たとえば「高校時代にボランティア活動をしていてこんなイベントを主催しました」とか、「鉄道が好きで高校時代に全国の駅を巡りました。大学では駅を中心とした都市工学について研究したいです!」とか、そういう生徒を積極的に取っていこうという考えです。
これからの大学はペーパーテストに強い生徒ではなく、そういう生徒を求めているということ。
ところが、こういう話をしても学歴信仰に取り憑かれている人たちはこう言います。「そんな制度ができてもそう簡単には変わらないでしょ。やっぱ王道は一般選抜だよ」。
でも驚くべきことに、私立大学における一般選抜での入学者は、総合型選抜の導入も進み、2024年には38.8%に激減。一般選抜はあっという間に大学入試の王道ではなくなってしまっています。
国立大学、私立大学ともに学校推薦型・総合型選抜の枠をさらに拡大していく方向に進んでいます。
つまり、高偏差値の進学校から一般選抜という道を選択した子たちは、より少ない枠を争う熾烈な競争をしなければならなくなるのです。
東洋経済オンライン
関連ニュース
- 大学入試「激変」40代以上の親が知らない最新事情
- 偏差値40台で一流大学に合格する子が続出する訳
- 高校時でわかる「大学までの人、大学からの人」の差
- 32歳校長「国公立大0→20人合格」させた凄い改革
- 入学志願者の減少が止まらない「薬学部」の実態
最終更新:4/8(火) 9:02